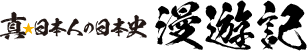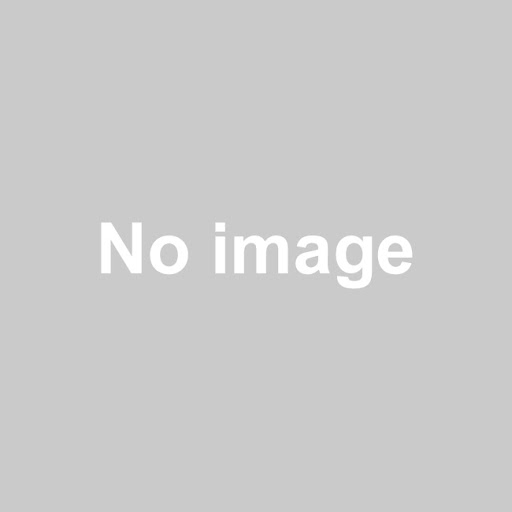肥後国は、江戸時代の三大飢饉にも餓死者を出さなかったという天下の美田地帯(名君細川重賢の功績も大)。邪馬台国を圧倒した狗奴国の比定地で(神武東遷は狗奴国からの逃避行か)、熊襲は大和朝廷に反抗し(クマソタケル)「肥後もっこす」の気風を醸成。平安中期には肥後北部に菊池氏が興り(狗奴国王ククチヒコの裔とも)、南北朝動乱では九州の南朝勢力を牽引、九州探題今川了俊に降伏しつつ肥後国守護に補され勢力を保つが、次第に豊後大友氏に圧迫され最後は大友から入嗣した菊池義武が甥の大友宗麟に滅ぼされた(米良氏を称する末孫が相良氏に庇護され旗本として存続。西郷隆盛も肥後菊池氏の裔を自称)。方や肥後南部では、人吉城の相良氏が阿蘇氏(阿蘇国造の裔で阿蘇神社神官)らを従え戦国大名へ台頭、島津義弘に敗れるも九州征伐に救われ、幕末まで人吉藩2万余石を保った。佐々成政の入封と破滅を経て、唐入りを目論む豊臣秀吉は肥後国を二分して子飼の加藤清正と小西行長に与え朝鮮役の前線で競わせるも、これが指揮系統混乱の一因となり無念の撤収。関ヶ原の戦いで行長が破滅し、肥後一国を領した清正は隈本を熊本に改め豪壮な熊本城を築くも、不肖の嗣子忠広が謀反ごっこを幕府に付込まれ改易。結局、熊本藩54万石は政界浮遊の達人 細川藤孝の手に帰した(初代藩主は孫の忠利)。明治維新後の熊本は鎮台・師団を擁する九州の中核都市となり(山陽新幹線開通で福岡へシフト)、「日本一の藩校」時習館・再春館の流れで教育機関も充実(北里柴三郎は熊本医大から東大進学)。熊本城跡の天守は復元ながら、築城名人 加藤清正が築いた石垣と重文の櫓群は健在で、清正公人気は今なお藩主細川家を圧倒。阿蘇山は日本有数の景勝地で、特に大観峰の景観は圧倒的、周辺には黒川温泉・杖立温泉・阿蘇白川水源・高千穂などが広がり一大観光エリアを形成している。方や、天草は海の景勝地、ヒラメなどの海産物も豊富で、車旅の名所。熊本旅行はドライブを軸に楽しみたい。
三池炭鉱万田坑
私評

三池炭鉱宮原坑跡・万田坑跡の世界遺産登録に伴い、観光地化を推進中。訪問の折には三川坑跡慰霊碑に手を合せたい(死者458名を出した三川炭鉱爆発事故…三井三池争議=サヨクによる現場破壊の爪痕)。レンガ建造物、地底坑口、機械室などが見所。史跡が徒歩圏にまとまっているので便利。